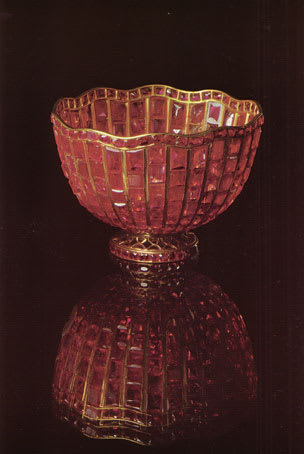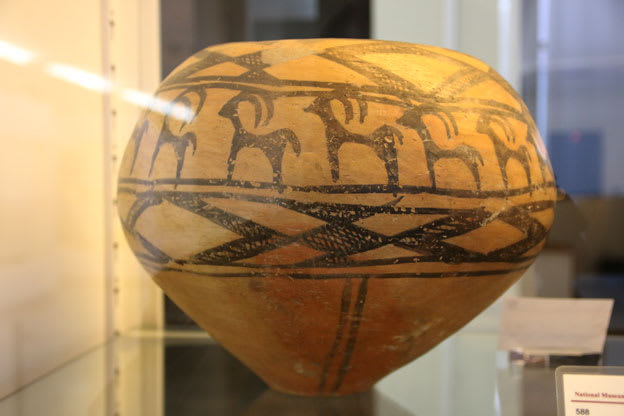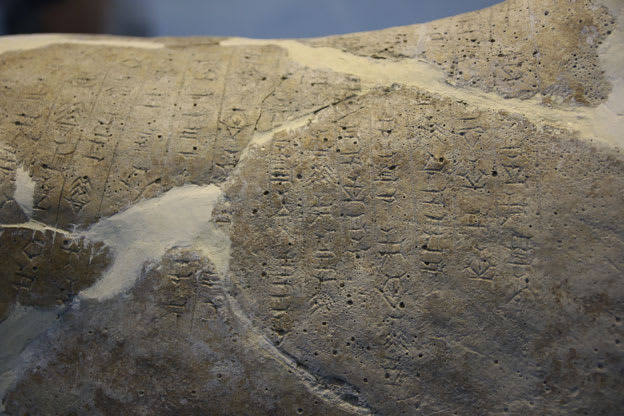パキスタンに続いてイランに出かけてきました。イランというよりもペルシャという響きに憧れを感じての旅立ちでした。
イラン8日間の旅でしたが、帰国時にドバイでの乗り継ぎができずに、1日遅れでの帰国になりました。ドバイでのホテル及び食事代はエミレーツ航空持ちであったので、そのおかげで簡単なドバイ観光もできました。
旅行日程は、以下のようなものでした。(航空機の時間は、予定のものです。)
「イラン8日間」(阪急旅行社) 2013年12月13日〜21日(航空機遅延のため1日延長)
第1日目 12月13日(金)
成田発 22:00 (EK0319)
第2日目 12月14日(土)
ドバイ着 5:00
ドバイ発 7:50 (EK0971)
テヘラン着 9:35
テヘラン市内観光(ゴレスタン宮殿、バーザール、宝石博物館、イラン考古学博物館)
テヘラン泊(TEHERAN ENGHELAB HOTEL)
第3日目 12月15日(日)
テヘラン発 7:20 (W51089)
シラーズ着 8:35
シラーズ観光(ナシールアルモスク、エラムガーデン、アリ・エブネ・ハムゼ廟、サアディー廟、コーラン門、ハーフェーズ廟、ヴァキールの市場)
シラーズ泊(PARS)
第4日目 12月16日(月)
ペルセポリス観光
ナクシュロスタム観光
パサルガダエ・キュロス王の墓
ヤズド泊(SAFAYIEH YAZD)
第5日目 12月17日(火)
ヤズド市内観光(沈黙の塔、ゾロアスター教寺院、ヤズド旧市街、金曜日のモスク、アミール・チャクマック広場)
イスファハン市内観光(金曜日のモスク、ヴァンク教会、イマーム広場の夜景)
イスファハン泊(KOWSAR ISFAHAN)
第6日目 12月18日(水)
イスファハン市内観光(チェヘルソトン庭園、マスジェディ・エマーム、アーリー・ガーブ宮殿、ハージュ橋、マスジェデ・スエイブ・ロトゥフォッラー)
イスファハン泊(KOWSAR ISFAHAN)
第7日目 12月19日(木)
アブヤネ村観光
カシャーン観光(テペ・シャルク、フィーン庭園)
テヘラン発 21:20 (EK0978)
ドバイ着 23:59
第8日目 12月20日(金)
ドバイ泊(マジェスティック・ホテル)
ドバイ観光(ブルジュ・ハリファ観光)
第9日目 12月21日(土)
ドバイ発 2:55 (EK0318)
成田着 17:20
成田出発が夜遅くのために、家を朝出ました。この日、強い低気圧が北海道を通過し、私は問題なく成田に到着できましたが、北海道から参加の二名がキャンセルし、一名は別便を利用して三日目から合流となり、全部で16名の小人数での観光になりました。
成田での待ち時間が長かったので、昼と夕食をとることになりましたが、幸いセブンイレブンがあるので、食料を買い込み、ビールも飲んで時間をつぶすことができました。レストランに入ると、飛行場値段で高いですしね。
タイムテーブルを見ると、ドバイ行きは、後ろから三番目の出発でした。観光客もあらかた出発した後で、出国手続きも簡単に済みました。
![]()
今回は、ドバイ経由でテヘランまで、エミレーツ航空の利用になりました。
![]()
エコノミークラスでも、このようなアメニティーグッズをもらうことができました。ベルト通し付きのポーチに、アイマスク、靴下、歯ブラシセット。なお、トルコ航空と違って、行きも帰りと同じ物でした。
もらうとうれしいのだけど、使わないのだよね。
![]()
成田からドバイへは、中国を西に横断してからパキスタンを南下するコースでした。シルクロードのルートと同じで、期待が高まりました。
エミレーツ航空は、ビデオが充実していましたが、iPODの音楽を聞きながらうつらうつらと過ごしました。
![]()
一回目の食事。グリル・チキンのプロヴァンス風ソース添えということです。もう一品は、牛肉の黒胡椒炒め。
美味しく食べましたが、食事とドリンクを配るのがえらく遅い。反対の列が食べ終わった頃に、ようやく配られました。
![]()
イランは、アルコール禁止で、持ち込みも法律で罰せられます。エミレーツ航空では、普通にビールやワインは提供されたので、しばしのお別れということで飲んだくれました。ビールは、ヴァドワイザーとハイネケンでした。
![]()
二回目の食事。真夜中で食欲もないので、少しでも食べやすいかと思って和食のサワラのグリルを選択しました。あまり美味しくなかったです。もう一品は、西洋アサツキが入ってオムレツ。今度はワインを飲みました。
![]()
ドバイ空港は、巨大で、建物内の装飾も凝っていました。
![]()
金持ちアラブ国の空港とあって、ブランド店も多く並んでいました。ブランド店は、素通りするだけですが。早朝にもかかわらず、乗客で空港内は賑わっていました。
![]()
アラブ風な壺も売っていました。
![]()
ベリーダンス用でしょうか、エロティックな衣装も展示されていました。
![]()
立派なクリスマスツリーも飾られていました。ここってイスラムの国ですよね。
![]()
空が明るくなったところで、再び飛行機に乗り込みました。
![]()
ドバイを飛び立つと、すぐにホルムズ海峡に出ました。眼下に見えているのはゲムシュ島のようです。ホルムズ海峡は、ペルシア湾沿岸諸国で産出する石油の重要な搬出路になっています。
現在では、イラン核開発問題のため、イランと欧米・湾岸アラブ諸国との間で緊張が高まっています。アメリカ海軍が展開し、これに対抗して、イランも定期的に海峡で軍事演習を行っている政治的緊張の場でもあります。
![]()
イラン内陸部に入ると、赤茶けた大地が広がるようになりました。
![]()
ドバイ・テヘラン間でも食事が出ました。朝食のためにオムレツでした。
![]()
![]()
航空機は、ザグロス山脈に沿うように北上しました。ザグロス山脈は、4000m級の山が連なり、雪で白く覆われていました。
今回のイラン旅行は、12月の寒い季節とあって、中東の国なら暖かいだろうと思って予約したのですが、良く調べると東京よりも寒いことが判りました。実際にも、観光中に寒くて苦労する場面もありました。
なお、果物のザクロは、このザグロス山脈の名前に由来するとも言われています。
![]()
イラン入国は、私の当たった管理官がコンピューターの照合に手間取ったかで時間がかかりましたが、なにがまずかったか判らないままに入国スタンプを押してくれました。運が悪いと、別室に連れて行かれて指紋採取が行われてしまようです。
荷物検査は、グループでまとまってからX線検査に向かうと、必要ないといってそのまま通してくれました。
イラン国内では、政府機関などは撮影禁止のため、少し離れてから空港を撮影しました。
テヘランまでは長旅でしたが、無事に入国し、さっそくテヘランの市内観光を始めました。