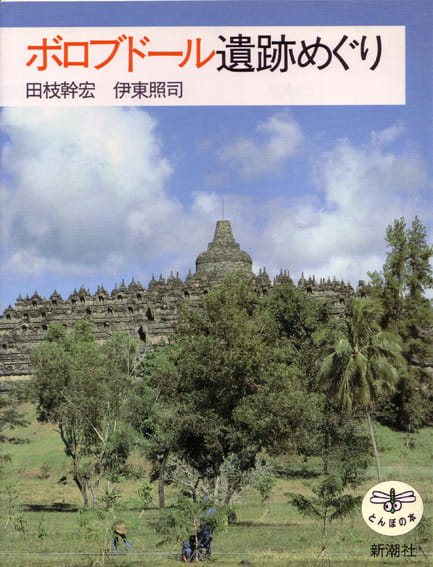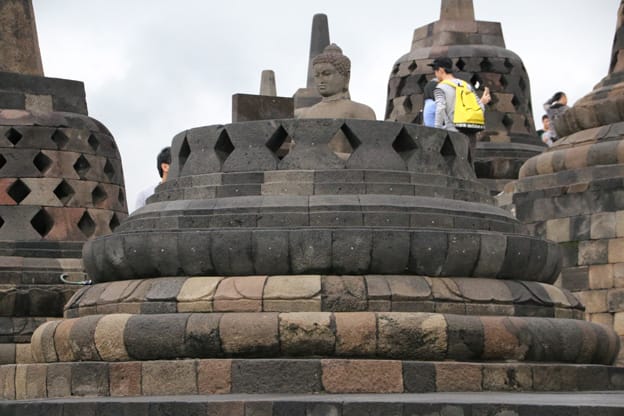シヴァ聖堂の見学を終えて、向かいあうナンディ堂を見学しました。最初に外見を見ていたので、内部に入りました。
内部には、シヴァ神の乗り物の聖牛ナンディの像が置かれていました。お堂いっぱいの大きさで堂々たる姿をしています。ナンディーあるいがナンディンとも呼ばれ、全ての四足動物の守護神とされています。シヴァ神ファミリーとして、ガネーシャと並んで一般大衆の人気を集めています。
ブラフマー神とビシュヌ神の乗り物は、ハンサ(鵞鳥)とガルダで、そのお堂が設けられていますが、中に収められていたはずの像は失われています。
![]()
ナンディ堂には、他にも像が飾られていました。
![]()
ヒンドゥー教の神様なのでしょうが、仏像といっても通りそうです。
![]()
続いて、ブラフマー聖堂を見学しました。
![]()
聖堂内部には、ブラフマー像が祀られていました。ブラフマー像は、4つの顔と4本の腕を持つ姿で現されます。
![]()
ブラフマー像の足元が気になって見ると、シヴァ聖堂と同じに、男性器のシンボルであるリンガと対をなす女性器のシンボルであるヨーニの形をしていました。
![]()
ブラフマー聖堂の回廊側壁では、シヴァ聖堂に飾られたラーマーヤナ物語のレリーフの続きが見られますが、これは先にまとめて掲示しました。
ブラフマー聖堂の外壁にも神々の像が飾られていました。
![]()
カーラ像でしょうか。カーラは、入口の門の上に飾られて平面的であることが多いですが、これは立体的になっています。
![]()
排水の樋の役目をしているマカラ像。
![]()
最後にヴィシュヌ聖堂。
![]()
ヴィシュヌ神は、一般には、4本の腕を持ち、右にはチャクラムと棍棒を、左にはパンチャジャナ(法螺貝)と蓮華を持つ男性の姿で表されます。そのためチャトゥルブジャ(4つの武器を持つ者)という称号も持っています。
![]()
この像の足元は、同様に、ヨーニの形をしています。リンガとヨーニは、シヴァ神のものと思っていましたが、もう少し一般的なものなのですかね。
![]()
マカラがいっぱい。
![]()
カーラ像も飾られていました。
![]()
北の出口の脇に立つ小堂ですが、先端が欠けています。
![]()
ブランバナン遺跡は、2006年5月27日に起きたジャワ島中部地震によって大きな被害をこうむり、この小堂の先端部もその際に落ちてしまったもののようです。
![]()
ロロジョングラン寺院の見学を終えて、北側の出口から出ました。
![]()
ロロジョングラン寺院を立ち去りがたく、振り返りつつ、ガイドの後をついていきました。
![]()
ロロジョングラン寺院は、見る方向によってお堂が重なるため、眺めも変わってきます。
![]()
ロロジョングラン寺院では、聖堂の内部やレリーフをしっかり見ることができて満足しました。他のツアーの旅行記を見ると、これだけたっぷりとは見学できないようです。
ただ、訪問一ヶ所目で早くも暑さが堪えて、体力的に厳しく感ずるようになってきました。
内部には、シヴァ神の乗り物の聖牛ナンディの像が置かれていました。お堂いっぱいの大きさで堂々たる姿をしています。ナンディーあるいがナンディンとも呼ばれ、全ての四足動物の守護神とされています。シヴァ神ファミリーとして、ガネーシャと並んで一般大衆の人気を集めています。
ブラフマー神とビシュヌ神の乗り物は、ハンサ(鵞鳥)とガルダで、そのお堂が設けられていますが、中に収められていたはずの像は失われています。

ナンディ堂には、他にも像が飾られていました。

ヒンドゥー教の神様なのでしょうが、仏像といっても通りそうです。

続いて、ブラフマー聖堂を見学しました。

聖堂内部には、ブラフマー像が祀られていました。ブラフマー像は、4つの顔と4本の腕を持つ姿で現されます。

ブラフマー像の足元が気になって見ると、シヴァ聖堂と同じに、男性器のシンボルであるリンガと対をなす女性器のシンボルであるヨーニの形をしていました。

ブラフマー聖堂の回廊側壁では、シヴァ聖堂に飾られたラーマーヤナ物語のレリーフの続きが見られますが、これは先にまとめて掲示しました。
ブラフマー聖堂の外壁にも神々の像が飾られていました。

カーラ像でしょうか。カーラは、入口の門の上に飾られて平面的であることが多いですが、これは立体的になっています。

排水の樋の役目をしているマカラ像。

最後にヴィシュヌ聖堂。

ヴィシュヌ神は、一般には、4本の腕を持ち、右にはチャクラムと棍棒を、左にはパンチャジャナ(法螺貝)と蓮華を持つ男性の姿で表されます。そのためチャトゥルブジャ(4つの武器を持つ者)という称号も持っています。

この像の足元は、同様に、ヨーニの形をしています。リンガとヨーニは、シヴァ神のものと思っていましたが、もう少し一般的なものなのですかね。

マカラがいっぱい。

カーラ像も飾られていました。

北の出口の脇に立つ小堂ですが、先端が欠けています。

ブランバナン遺跡は、2006年5月27日に起きたジャワ島中部地震によって大きな被害をこうむり、この小堂の先端部もその際に落ちてしまったもののようです。

ロロジョングラン寺院の見学を終えて、北側の出口から出ました。

ロロジョングラン寺院を立ち去りがたく、振り返りつつ、ガイドの後をついていきました。

ロロジョングラン寺院は、見る方向によってお堂が重なるため、眺めも変わってきます。

ロロジョングラン寺院では、聖堂の内部やレリーフをしっかり見ることができて満足しました。他のツアーの旅行記を見ると、これだけたっぷりとは見学できないようです。
ただ、訪問一ヶ所目で早くも暑さが堪えて、体力的に厳しく感ずるようになってきました。