入口から本堂へは、トンネル状の通路を通りますが、豪華な装飾が施されていました。
![]()
仏歯は二階の礼拝堂に収められていますが、一階にも礼拝堂が設けられていました。
![]()
前に飾られている象牙は、ペラヘラ祭りに使われた象のもののようです。
![]()
扉の上には、これまで見てきたスリランカの寺院でおなじみになった、魔除けの像が置かれていました。
![]()
木造の礼拝堂は、全体に装飾が施されていました。
![]()
日本の寺院建築と似た雰囲気があります。
![]()
二階の礼拝堂を見上げたところ。
![]()
二階へと進みます。
![]()
踊り場には、ペラヘラ祭りの際に仏歯を収めるための容器が展示されていました。
![]()
このレリーフは、スリランカへ仏歯が持ち込まれた際の逸話を現したものです。
インドで仏陀が火葬された後、遺骨と歯はインド各地に分割されました。4世紀に南インドのカリンガ王が戦に敗れた際、娘のヘーマ・マーラと夫のダンタはスリランカへ逃れましたが、その際、マーラは父の遺言に従って長い髪を巻きあげた中に仏歯を隠してセイロンに持ち込み、アヌラータブラに奉納しました。
その後、仏歯は王権の権威を保証する証となり、都が移る度に一緒に運ばれて、最後はキャンディに落ち着きました。
なお、収められている仏歯は、右の犬歯とのこと。
この仏歯伝来伝説は、ホータン王に嫁ぐ中国の王女が、髪飾りに隠して絹の繭を持ってきたことによって、1世紀頃に中国外で絹の生産が行われるようになったという伝説を思い起こさせます。
![]()
ペラヘラ祭りに使われる飾りのようです。
![]()
二階の礼拝堂に進みました。
![]()
仏歯を収めた容器は、プージャの際に扉が開かれて見ることができますが、その時間ではありませんでした。写真が展示してありましたが、宝石で飾られた黄金の容器のようです。
![]()
熱心に礼拝する信者で混み合っていました。
![]()
豪華に装飾された礼拝堂。扉の奥に仏歯が収められています。
![]()
お供えの花も沢山置かれていました。
![]()
廊下いっぱいに信者が座っていました。
![]()
一階に下りる途中にも礼拝堂が設けられていました。

仏歯は二階の礼拝堂に収められていますが、一階にも礼拝堂が設けられていました。

前に飾られている象牙は、ペラヘラ祭りに使われた象のもののようです。

扉の上には、これまで見てきたスリランカの寺院でおなじみになった、魔除けの像が置かれていました。

木造の礼拝堂は、全体に装飾が施されていました。

日本の寺院建築と似た雰囲気があります。

二階の礼拝堂を見上げたところ。

二階へと進みます。

踊り場には、ペラヘラ祭りの際に仏歯を収めるための容器が展示されていました。

このレリーフは、スリランカへ仏歯が持ち込まれた際の逸話を現したものです。
インドで仏陀が火葬された後、遺骨と歯はインド各地に分割されました。4世紀に南インドのカリンガ王が戦に敗れた際、娘のヘーマ・マーラと夫のダンタはスリランカへ逃れましたが、その際、マーラは父の遺言に従って長い髪を巻きあげた中に仏歯を隠してセイロンに持ち込み、アヌラータブラに奉納しました。
その後、仏歯は王権の権威を保証する証となり、都が移る度に一緒に運ばれて、最後はキャンディに落ち着きました。
なお、収められている仏歯は、右の犬歯とのこと。
この仏歯伝来伝説は、ホータン王に嫁ぐ中国の王女が、髪飾りに隠して絹の繭を持ってきたことによって、1世紀頃に中国外で絹の生産が行われるようになったという伝説を思い起こさせます。

ペラヘラ祭りに使われる飾りのようです。

二階の礼拝堂に進みました。

仏歯を収めた容器は、プージャの際に扉が開かれて見ることができますが、その時間ではありませんでした。写真が展示してありましたが、宝石で飾られた黄金の容器のようです。

熱心に礼拝する信者で混み合っていました。

豪華に装飾された礼拝堂。扉の奥に仏歯が収められています。

お供えの花も沢山置かれていました。

廊下いっぱいに信者が座っていました。

一階に下りる途中にも礼拝堂が設けられていました。








































































































































































































































































































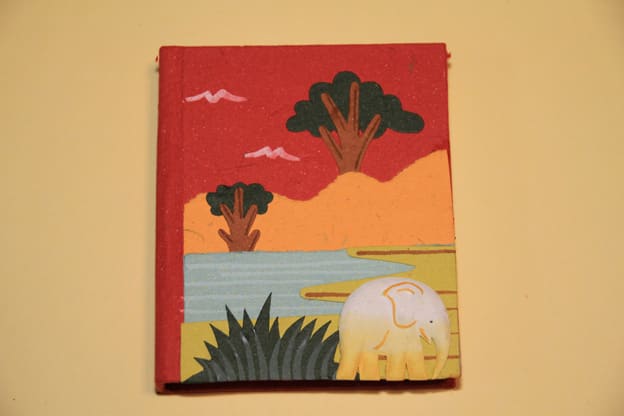



























 77
77
















































































































