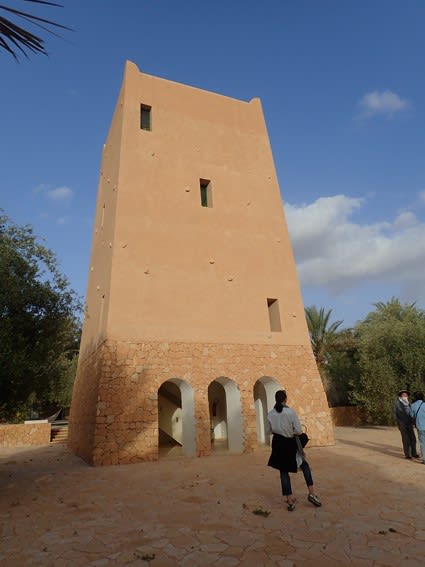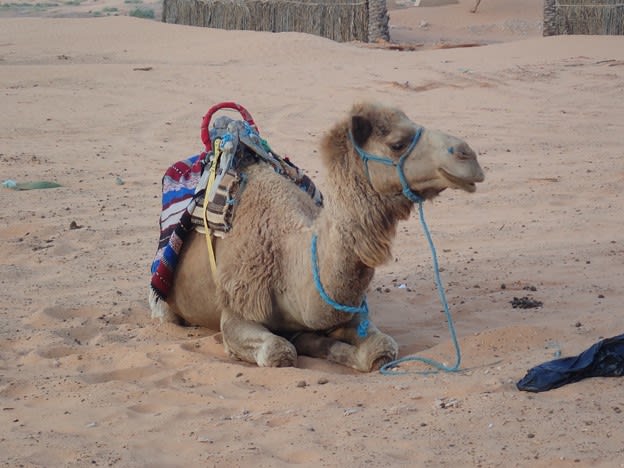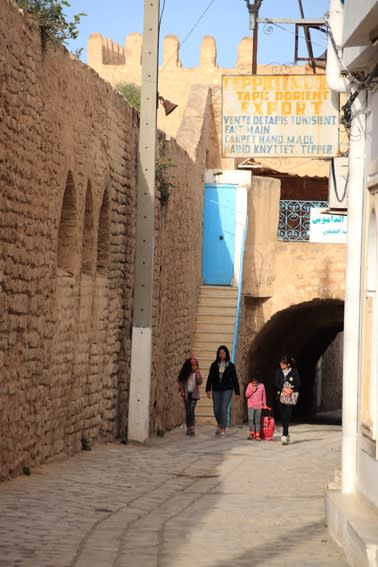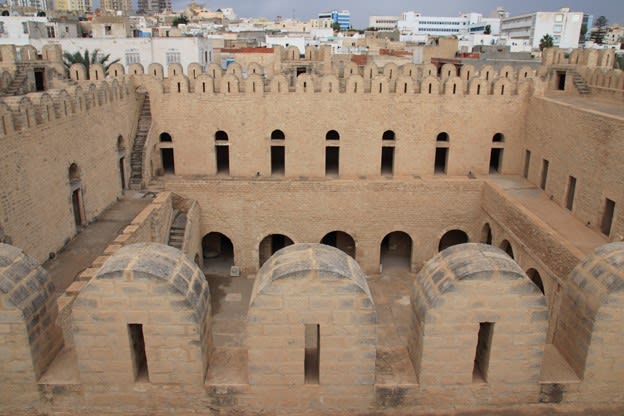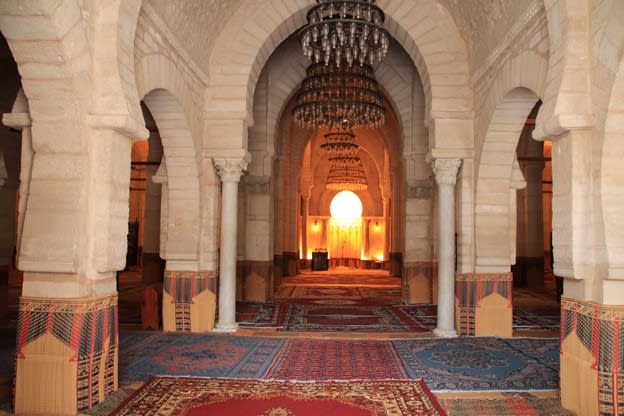トズールの旧市街に到着してバスを降り、まずウルド・エル・ハデフ地区に向かいました。
![]()
ウルド・エル・ハデフ地区は、14世紀に造られた古い地区で、幾何学的な模様を描く装飾レンガが特徴になっています。
![]()
ゲートをくぐって小路に進みました。
![]()
一時は荒廃が進んでいたようですが、現在はきれいに修復されて、土産物屋が店を開いています。
![]()
![]()
壁には花やアラビア語、ベルベルのシンボルが描かれています。
![]()
アーチを度々くぐっていくことになりました。
![]()
![]()
人もあまり歩いておらず、時が止まったような静かな空間が広がっていました。
![]()
![]()
![]()
土産物屋の商品が壁に掛けられていました。
![]()
静かな脇道。
![]()
![]()
ネコも風景の欠かせないパーツになっています。
![]()
模様にも家紋のような意味が込められているのかも知れませんが、そこまでは判りませんでした。
![]()
観光客の顔を見るのも少ないのか、子供が興味深そうにこちらを見ていました。
![]()
ここの装飾は、ひと際見事です。
![]()
![]()
ウルド・エル・ハデフ地区の出口。案内が無いと、ここは入り方が判らないかもしれません。

ウルド・エル・ハデフ地区は、14世紀に造られた古い地区で、幾何学的な模様を描く装飾レンガが特徴になっています。

ゲートをくぐって小路に進みました。

一時は荒廃が進んでいたようですが、現在はきれいに修復されて、土産物屋が店を開いています。


壁には花やアラビア語、ベルベルのシンボルが描かれています。

アーチを度々くぐっていくことになりました。

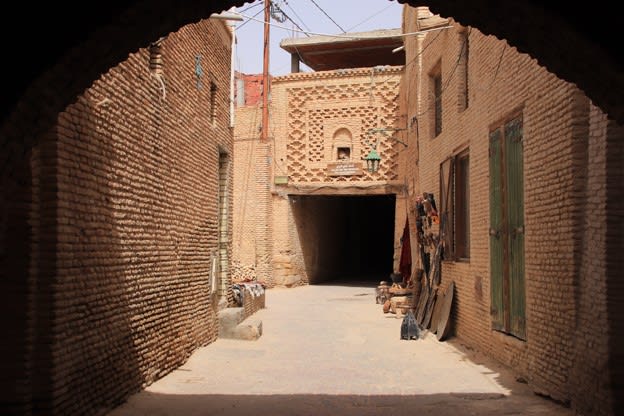
人もあまり歩いておらず、時が止まったような静かな空間が広がっていました。



土産物屋の商品が壁に掛けられていました。

静かな脇道。


ネコも風景の欠かせないパーツになっています。

模様にも家紋のような意味が込められているのかも知れませんが、そこまでは判りませんでした。

観光客の顔を見るのも少ないのか、子供が興味深そうにこちらを見ていました。

ここの装飾は、ひと際見事です。


ウルド・エル・ハデフ地区の出口。案内が無いと、ここは入り方が判らないかもしれません。